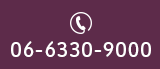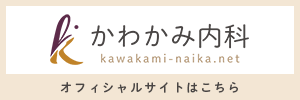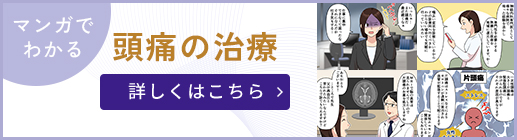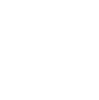メディア記事
【院長ブログ】脂質異常症(高脂血症)について(原因と症状)
2026.01.14
高脂血症は2007年より脂質異常症と名称が改められた病気です。動脈硬化の危険な原因でもあり、放置すれば脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患をまねく原因となります。そこで今回は“脂質異常症(高脂血症)について”その原因と症状についてお伝えします。高脂血症から脂質異常症と診断名が変わりました。以前は高脂血症と呼ばれており、総コレステロール値、中性脂肪値、LDLコレステロール値のいずれかが高いか、HDLコレステロール値が低いことが診断基準とされていました。しかし、総コレステロール値が高い人のなかには、…【院長ブログ】高血圧症の治療法
2025.12.05
生活習慣病の一つである高血圧症の診断を受ける方は多いです。高血圧症は、放っておくと重大な疾患につながる怖い病気。高血圧の治療法には、生活習慣の見直しと薬物療法の2つがあります。どれも糖尿病や心臓病、脳梗塞など全ての生活習慣病の予防や改善に重要なことです。そこで今回は、“高血圧症の治療”についてお伝えします。高血圧症の治療法①生活習慣の見直し生活習慣ですが、次のような6つがあります。それぞれのポイントをお伝えしますので、元気で長生きのためにはこれらを実行されることをおすすめします。塩分制限塩分制限…【院長ブログ】高血圧症について(原因と症状)
2025.11.13
そのまま放置すると重大な病気を引き起こすとされる高血圧症。今回はその“高血圧症について”の原因と症状、診断についてお伝えします。高血圧症とは?体を動かしたり寒さを感じたりすると一時的な血圧上昇が起こりますが、高血圧症という病気は安静時でも慢性的に血圧が高い状態が続いていることをいいます。収縮期血圧は140mmHg以上、拡張期血圧は90mmHg以上の場合をいい、どちらか一方でもこの値を超えていると高血圧症と診断されます。高血圧症の原因とは?心臓から血液を送り出すときの血液によって血管の壁にかかる圧…【院長ブログ】糖尿病の治療法
2025.10.11
糖尿病(2型糖尿病)の治療には、①食事療法、②運動療法、③薬物療法という三本柱があります。今回は“糖尿病の治療法”について、方法ごとにお伝えします。①食事療法食事療法をおこなう前に現在の食生活を見直し、治療に対する動機づけをおこない、治療を習慣化することが必要です。具体的にポイントは次のようになります。・食生活の見直し…患者さん自身に食事内容を記録してもらい、食生活のどこに問題があるかを検討する・治療に対する動機づけ…糖尿病はどうして治療をする必要があるのかを理解するために、適切な食事療法をおこ…【院長ブログ】糖尿病について(原因と症状)
2025.09.09
糖尿病には、大きく分けて1型と2型の2つのタイプがあります。体内のインスリンの活動に問題が生じ、摂取した食物エネルギーを正常に代謝できなくなる病気です。糖尿病と上手に付き合っていくためには、糖尿病についての正しい知識を増やすことが大切です。今回は“糖尿病について”そのタイプごとに原因や前兆などをお伝えします。1型糖尿病1型糖尿病とは、すい臓が自分ではインスリンを作ることができない病気で、以前はインスリン依存型糖尿病という病名で呼ばれていました。したがって、それを補うためにインスリンの注射をしなけ…【院長ブログ】塩分制限
2025.08.03
塩分の摂り過ぎは血圧を上げ、心臓病や脳卒中の危険性を非常に高めます。血圧管理と病気の予防のためには、食塩制限を含めた質の良い生活習慣を継続することが大切です。そこで今回は、“塩分制限”についてその必要性をお伝えします。まずはあなたの食生活の食塩摂取量をチェック!まずはあなたの食生活での食塩摂取量をチェック!次の10個の項目のうち、当てはまるものにチェックマークをつけてみましょう。かるしおチェックシート(国立循環器病研究センター作成の「かるしおプロジェクト」より抜粋) 味噌汁やスープを1日2回は飲…【院長ブログ】脳梗塞
2025.07.04
脳梗塞は、以前は日本人の死因の上位占めていましたが、救急医療の充実や治療法の進歩により、亡くなる患者さんが少なくなったと言われています。この病気は後遺症を残してしまう恐れのある依然として怖い病気であることにはちがいありません。そこで今回は、“脳梗塞”について、病態や後遺症についてお伝えします。脳梗塞とは?脳梗塞とは脳の血管が突然つまって血流が途絶え、脳の細胞が死んでしまう病気(壊死)です。早期に適切な治療を受けないと後遺症を残し、死亡してしまう可能性があります。脳梗塞の種類は3つ!脳梗塞には血管…【院長ブログ】心筋梗塞
2025.06.11
命の危険がある怖い病気として心筋梗塞があげられます。今回はその“心筋梗塞”について、症状、治療や予防についてお伝えします。心筋梗塞とは?心筋梗塞とは、血管内がプラークや血栓などで詰まり、冠動脈内の血流がなくなってしまい、心筋に栄養と酸素が十分に届かず、心筋そのものが壊死をおこした状態をいい緊急の対処が必要な病気です。心筋梗塞の症状や特徴は?症状や特徴は次のとおりです。・突然の押しつぶされるような胸の痛み・締め付けられるような胸の痛み・焼けるような胸の重苦しさ・冷や汗・吐き気・嘔吐・症状は30分以…【院長ブログ】狭心症
2025.05.07
循環器の病気に“狭心症”というものがあります。今回は、その“狭心症”について、狭心症の種類と治療についてお伝えします。狭心症とは?心臓がたゆみなく動き続けるために、心筋へ酸素と栄養素を送るための専用栄養血管が冠動脈です。この冠動脈が細くなるために心筋への血流が阻害され酸素不足が起こり、胸の痛みなどを生じるのが狭心症です。狭心症には4種類あります。それぞれについて、次に詳しくお伝えします。狭心症の種類①労作性狭心症階段を上がること、重たいものを持つこと、運動をすること、心理的なストレスを受けること…【院長ブログ】糖尿病
2025.04.11
糖尿病とは、インスリンというホルモンが十分に働かず、血液中を流れるブドウ糖の量(血糖)が増えてしまう病気です。何年間も放置されると、血管が傷つき、進行すると重い病気を引き起こします。そこで今回は、“糖尿病”について原因や症状、種類についてお伝えします。糖尿病になる2つの原因糖尿病になるとインスリンが十分に働かず、糖をうまく細胞内に取り込められなくなるため、血液中に糖があふれかえってしまいます。これには、2つの原因があり、糖尿病ではこの2つの原因の影響が血糖値を高くします。インスリン分泌低下膵臓の…