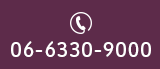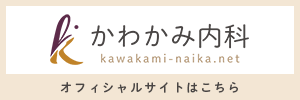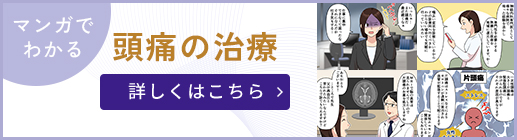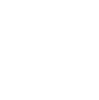メディア記事
【院長ブログ】糖尿病
糖尿病とは、インスリンというホルモンが十分に働かず、血液中を流れるブドウ糖の量(血糖)が増えてしまう病気です。何年間も放置されると、血管が傷つき、進行すると重い病気を引き起こします。そこで今回は、“糖尿病”について原因や症状、種類についてお伝えします。
糖尿病になる2つの原因
糖尿病になるとインスリンが十分に働かず、糖をうまく細胞内に取り込められなくなるため、血液中に糖があふれかえってしまいます。これには、2つの原因があり、糖尿病ではこの2つの原因の影響が血糖値を高くします。
インスリン分泌低下
膵臓の機能の低下により、十分なインスリンを作れなくなってしまう状態。例えば血液中の糖が細胞のドアを開ける鍵を持っていない状態で、鍵を持たない糖が中に入ることができず、血液中にあふれてしまいます。
インスリン抵抗性
インスリンは十分な量が作られているけれども、効果が発揮できていない状態。運動不足や食べ過ぎが原因となり肥満になると、インスリンの働きが弱まります。
糖尿病の症状ってどんなもの?
糖尿病は、血糖値が非常に高くならなければ症状が現れてきません。そのため、気付いた時には進行している場合が多いです。高血糖における症状は、次のようなものがあります。
・喉が渇く、水をよく飲む
・尿の回数が増える
・体重が減る
・疲れやすくなる
・血糖値が非常に高い場合は、意識障害がおこる
糖尿病ってどんな種類があるの?
糖尿病は、いくつかの種類に分類され、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の特定の機序や疾患によるもの、妊娠糖尿病と分類することができます。それぞれについて詳しくお伝えします。
1型糖尿病
1型糖尿病では、膵臓からインスリンがほとんど出なくなる(インスリン分泌低下)ことにより血糖値が高くなります。生命の維持には、インスリンを注射で補う治療が必須。
2型糖尿病
2型はインスリン非依存型とも呼ばれ、遺伝的要因に過食や運動不足などの生活習慣が重なって発症します。注射や飲み薬なども必要に応じて利用。多くは2型であり、日本ではその疑いがある人(可能性を否定できない人を含む)は成人の6人に1人、約1870万人にのぼっています。
その他の特定の機序や疾患によるもの
膵外分泌疾患・内分泌疾患・肝疾患・薬剤や化学物質によるもの・感染症など
妊娠糖尿病
妊娠中は絶えず赤ちゃんに栄養を送っているため、お腹が空いているときの血糖値は、妊娠していないときと比べると低くなります。一方、胎盤からでるホルモンの影響はインスリンを効きにくくし、食後の血糖値を上昇しやすくします。血糖値の高値は出産後には元に戻りますが、妊娠糖尿病を経験したかたは将来糖尿病に罹りやすいといわれています。